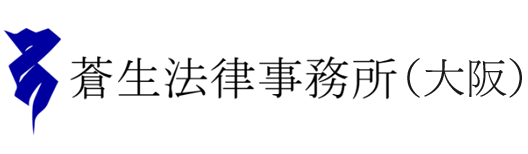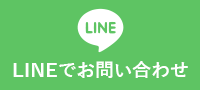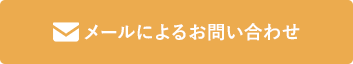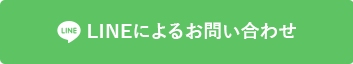BLOG・導入事例
弁護士が解説!退職代行における法的リスクとは

こんにちは。蒼生(そうせい)法律事務所の弁護士、泉 宏明(いずみ ひろあき)です。
「会社を辞めたいけれど、上司に言い出せない…」 「退職の話をしたら、引き止められて辞めさせてもらえない…」
こんな悩みを抱える方にとって、「退職代行サービス」は非常に心強い味方に見えますよね。最近、特に若い世代を中心に利用が広がっています。
しかし、「退職代行サービス」に関して、先日驚きのニュースが飛び込んできました。今回は、このニュースをきっかけに、退職代行サービスに潜む「法的なリスク」について、弁護士の視点から分かりやすく解説していきます。
① ニュース概要:大手退職代行業者に「弁護士法違反」の疑い
まず、今回報じられたニュースの概要です。
| 日付 | 2025年10月22日 |
|---|---|
| 内容 | 警視庁は22日午前、報酬を得る目的で依頼者を弁護士に紹介したとして、退職代行サービス「モームリ」を運営するアルバトロス(東京・品川)などを弁護士法違反容疑で家宅捜索した。捜査関係者への取材でわかった。同庁は押収した資料を分析するなどして、刑事責任を問えるかどうか調べる。 |
| 出典 |
「退職代行モームリ」を家宅捜索、報酬目的で弁護士紹介疑い 警視庁(日本経済新聞) 記事リンクはこちら |
② なぜ今、退職代行が注目されるのか

このニュースがなぜこれほど大きく取り上げられるのでしょうか。
それは、退職代行サービスがここ数年で急速に市場を拡大し、非常に多くの人が利用する「身近なサービス」になっていたにもかかわらず、警察の捜査の対象となったからではないでしょうか。
- 高まる需要: いわゆる「ブラック企業」の問題や、人手不足による強引な引き止め(退職妨害)、あるいは「上司と話すこと自体が極度のストレス」と感じる方々にとって、本人に代わって退職の意向を伝えてくれるサービスは、まさに救世主のような存在でした。
- 業界の急成長: 需要の高まりを受け、非常に多くの事業者が退職代行サービスに参入しました。料金も数万円程度と、弁護士に依頼するよりも手軽なイメージがあったため、利用者が急増していました。
- グレーゾーンの問題: しかし、弁護士たちの間では「それは違法じゃないか?」と以前から警鐘が鳴らされていました。今回、業界大手とも言える「モームリ」に捜査のメスが入ったことで、この業界全体の「グレーゾーン」の問題が一気に表面化したともいえるでしょう。
当然ながら、本投稿作成時においては捜査段階であり、犯罪であると裁判所が判断するか、そもそも検察が起訴するかどうかは決まっていません。とはいえ、弁護士間ではやはり捜査が入ったかという感想を抱く人が多いのではないかと思います。
③ 専門的視点:危険な「非弁行為」とは?
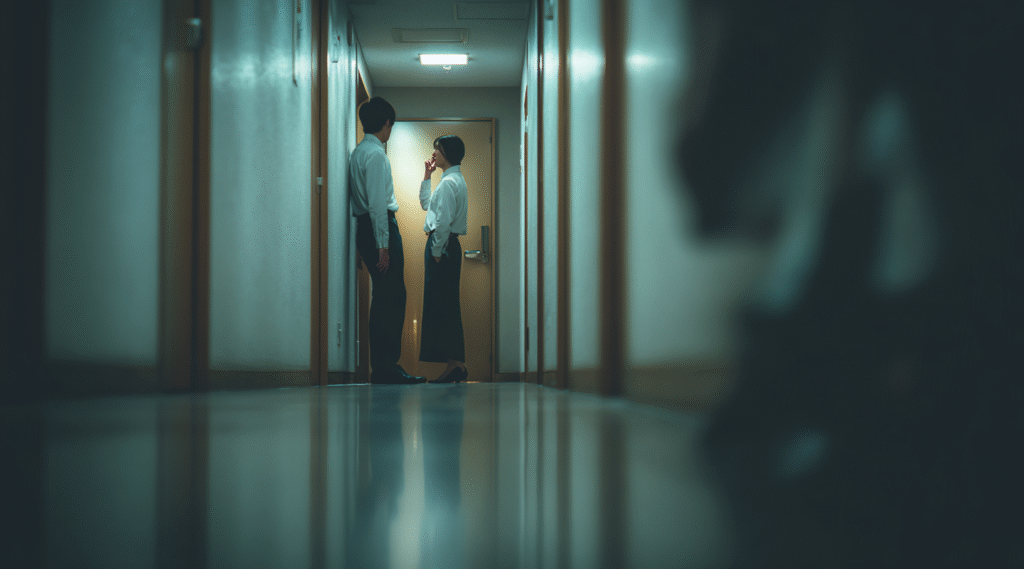
さて、ここからが本題です。 ニュースで何度も出てくる「弁護士法違反」や「非弁行為(ひべんこうい)」とは、一体何なのでしょうか。
弁護士法とは? なぜ「弁護士」しかダメなのか?
まず、「弁護士法」という法律があります。 この法律は、弁護士が守るべきルールや弁護士でなければ出来ないことを定めています。
お金が絡むトラブルや、権利の主張(「未払い残業代を払え!」など)は、法律に基づいた専門的な知識や、高度な倫理観が必要です。 もし、法律知識のない人が法律に基づかない交渉をしたり、悪質な業者が間に入って依頼者から高額な手数料だけ取って逃げてしまったら… 依頼者(あなた)が守られるべき権利を守れず、かえって大きな損害を被ってしまいます。
そうした危険を防ぐため、「報酬(お金)をもらって、法律トラブルの相談や交渉ごと(=法律事務)を仕事にできるのは、弁護士(や弁護士法人)だけですよ」と定めているのです(一定金額以下の紛争は司法書士の先生方も扱うことが出来ます)。
危険な「非弁行為」とは
「弁護士ではない人が、報酬をもらって法律事務をやってしまうこと」を、法律用語で「非弁行為(ひべんこうい)」と呼びます。これは、弁護士法第72条で禁止されています。
【出典】 弁護士法 第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。(以下略)
出典:弁護士法(e-Gov法令検索)、https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
「法律事務」とか「法律事件」とか、難しい言葉が並んでいますが、退職代行に当てはめてみましょう。
- 報酬を得る目的で: → 利用者が退職代行業者に「代行費用」を支払うこと。
- 法律事件に関して: → 会社側と何らかの「モメごと(紛争)」が発生している、または発生しそうな状態。 (例:「未払い残業代がある」「有給を使わせてもらえない」「辞めたら損害賠償請求すると言われた」など)
- 法律事務を取り扱う: → 本人に代わって「交渉」や「請求」を行うこと。
つまり、退職代行の業者が、報酬を得る目的で、単なる「使者」(本人の退職の意思を会社に伝達するだけの者)を超えて、会社側と何らかの「交渉」をした瞬間に、非弁行為(違法)になり得るのです。
退職代行の「セーフ」と「アウト」の境界線
では、具体的にどこまでがセーフで、どこからがアウトなのでしょうか。
【セーフ 🙆♀️】 単なる「使者(ししゃ)」としての連絡
- 「〇〇さんから依頼を受け、退職届を預かりましたのでお送りします」
- 「〇〇さんは、民法627条に基づき、本日より2週間後のX月X日をもって退職する意向です」
これらは、本人の「決定した意思」を代わりに伝えているだけ(=使者)なので、セーフとされています。 そもそも、法律上、退職は労働者の自由な権利です(※期間の定めのある雇用契約においてはそうではない場合がありますが)。会社側の「承諾」は必要なく、一方的な意思表示から2週間(※正社員など期間の定めのない契約の場合)で雇用契約が終了します。
【出典】 民法 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
出典:民法(e-Gov法令検索)、https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
【アウト 🙅♂️】 「交渉」や「法律的な主張」
- (有給の交渉)
会社:「人手が足りないから、有給消化は認めない」
業者:「いえ、有給取得は労働者の権利です。すべて消化させてください」
↑ これはもう「交渉」であり「法律的な主張」です。完全にアウトです。 - (未払い残業代の請求)
業者:「〇〇さんの計算では、未払い残業代が30万円あります。退職金と合わせて振り込んでください」
↑ 「請求」は、まさに法律事務そのものです。アウトです。 - (退職日の交渉)
会社:「引き継ぎが終わるまで、2ヶ月は辞めさせない」
業者:「それは困ります。1ヶ月で退職できるよう調整してください」
↑ これも「交渉」です。アウトです。 - (損害賠償への対応)
会社:「急に辞めたら損害賠償もんだぞ!」
業者:「そのような請求に法的な根拠はありません」
↑ 法律的な見解を述べて反論しています。アウトです。
ニュースになった業者は、まさにこの「アウト」の領域に踏み込んでいた疑いがある、ということです。
④ あなたが「違法な業者」に頼むとどうなる?

「業者が違法なのは分かったけど、依頼するこっち(読者)に何かデメリットはあるの?」
とてもデメリットがあります。 ここが一番知ってほしいポイントです。
違法な非弁行為を行った業者(弁護士ではない民間企業)が会社と「交渉」しても、その交渉は法律上「無効」です。
どういうことか。 例えば、あなたが未払い残業代30万円を請求したかったとします。
- パターンA:弁護士に依頼した場合
弁護士が法に基づいて会社と交渉し、「30万円を支払う」という合意(和解)を取り付けた。
→ この合意は法的に有効です。会社は支払う義務を負います。 - パターンB:違法な(非弁)代行業者に依頼した場合
業者が会社と交渉(?)し、「分かりました、30万円払います」と会社が言った。
→ この合意は、非弁行為によるもので法的に無効です。 後から会社が「やっぱり払いません」と言い出しても、法的には「合意が成立していない」ことになります。
あなたは業者に代行費用を払ったのに、結局、何も解決していないという最悪の事態になりかねません。それどころか、本来もらえるはずだった残業代をもらい損ねる(時効が過ぎてしまうなど)危険すらあるのです。
どうやって業者を選べばいい?
では、私たちはどうすれば良いのでしょうか。 ポイントは「誰が運営しているか」です。
安全な業者を見分けるポイント
×
△
◎
- 民間企業(株式会社、合同会社など)
→ 「交渉」や「請求」は一切できません。
→ 「退職の意思を伝えるだけ」の「使者」として割り切って使うならOKです。「有給消化や残業代の交渉もします!」と書いてあれば、それは非弁行為(違法)の可能性が極めて高いです。 - 労働組合
→ 労働組合法に基づき、会社と「団体交渉」する権利を持っています。
→ したがって、有給消化や未払い賃金の「交渉」が可能です。ただし、あくまで「交渉」ができるだけで、「訴訟」の代理はできません。また、労働組合の名前を借りていても実質的に労働組合と言えない場合もありうると考えられます。 - 弁護士(法律事務所)
→ 言うまでもなく「法律事務」の専門家です。
→ 「交渉」も「請求」も、その後の万が一の「訴訟」も、すべてを行うことが出来ます。
もしあなたが、「ただ辞意を伝えてくれれば、あとは何もいらない」という状況なら、①の民間企業のサービスでも良いかもしれません
しかし、多くの方は出来るならば「未払い残業代も請求したい」「有給を全部使いたい」「会社から損害賠償とか言われそうで怖い」などの要望をお持ちなのではないでしょうか。
何らかの「交渉」が必要になりそうな場合は、①の民間企業に頼むことは問題を孕みます。 「交渉」が必要になりそうな場合は、③の弁護士(法律事務所)が運営するサービスを選んでいただければと思います。
⑤ 今後の展望

退職代行業者は「モームリ」だけではありません。今後、同業他社も捜査の対象となる可能性があります。
「安くて手軽そうだから」という理由だけで業者を選ぶのは非常に危険です。 業者が「交渉します」と謳っていても、それが法的に許された運営主体なのかを、必ず確認してください。
そもそも、退職は労働者に認められた正当な権利です。 本来的には、代行サービスなど使わずに退職できるのが一番です。しかし、ご自身で退職の意向を伝えること自体が難しい方もおられるかと思います。未払い残業代がある場合も往々にして見受けられます。労働問題でトラブルを抱えている方には、弁護士にご相談いただきたいと思います。
蒼生法律事務所は、あなたの正当な権利を守るため、法的な観点から最適なサポートを提供します。